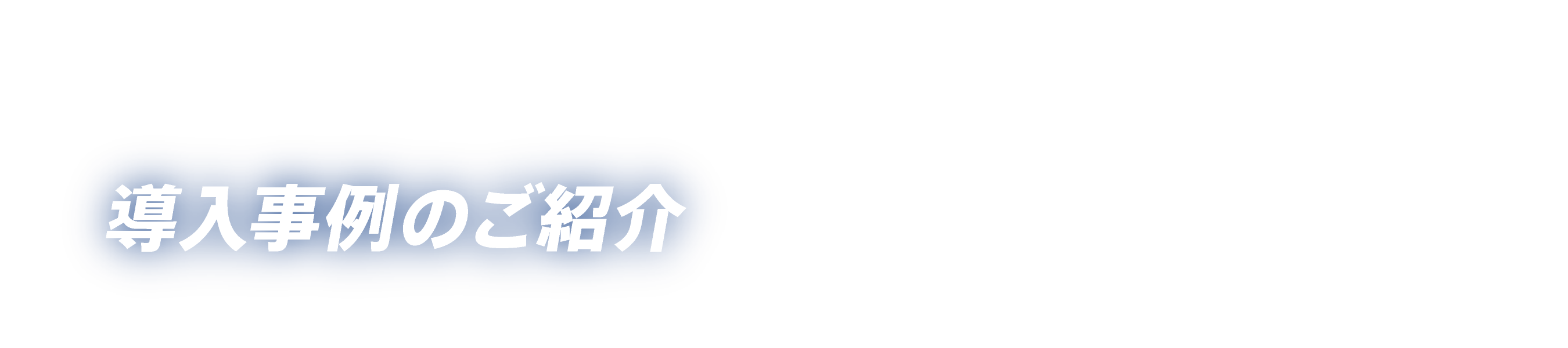横浜市立
新羽小学校
ALPHAを使ってタグラグビーの競技力アップ!!
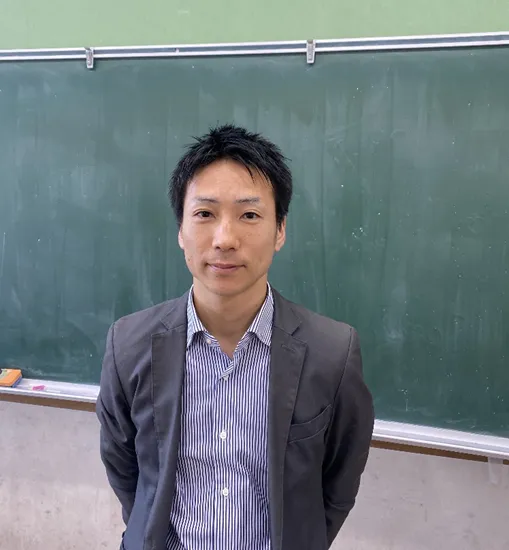
今回インタビューを受けてくださったのは、横浜市立新羽小学校のK・N先生。現在、3年生の学年主任と情報部員を務める。横浜市情報教育リーダー、日本スポーツ協会公認スポーツリーダー、全国放送研究会連盟事務局員、横浜市小学校情報研究会幹事も兼任する。
ALPHAを使ったきっかけはタグラグビーの競技力向上
ALPHAを使ったきっかけは、研究大会(※1)でタグラグビーをやることになり、どのようにやるかを模索していた時期にPestalozzi Technology(以下、PT)の社員と話す機会があったからです。当初は複数のプロラグビーチームに技術的な指導をしてもらう予定で、その動きをドローンで俯瞰的に撮って検証し、プログラグビーというAIでシミュレーションすることを想定していました。しかし、AIシミュレーションで思考力を働かせて動きのイメージをつかみ、ドローンで分析をしても、肝心な体力や技術が向上しなくては上手くいきません。PTに協力してもらったのは、体力テストの種目がタグラグビーにどのように関わるか、例えば握力は「ボールキャッチ」「タグをつかむ」、シャトルランは「コートの中で走り続ける持久力」につながるなど、どのような要素が必要で、何を鍛えれば、どのようにタグラグビーに活かせるかを一緒に紐解いてくれました。
※1 研究大会…特定非営利活動法人COLLECTIVEが運営するEIC TOKYOイベント
体力テストを通して自分の特徴を知る
実際に体力テストALPHAを使ってみて、1年生から6年生まで全校で健康増進や体力向上を手助けできる便利なツールだと思いました。私としては体力テストALPHAを使うことが主目的ではなく、あくまでもタグラグビーのための運動能力・技能の向上が目的で、その手段として体力テストALPHAを使いましたが、例えば子どもたちは握力を鍛える運動動画を見て、「じゃあ実際にこれを家でやってみよう」と、自発的に運動に取り組むことができます。
私はタグラグビーのチーム編成を考える際に、ALPHAを活用して50m走の結果をもとに力の差が均等になるように振り分けました。運動が得意でない子にも参加してもらえるような授業にしたかったのですが、子どもたちはチームの中でそれぞれの役割を話し合い、「足が速い子はボールを運ぶ」「自分は走るのが苦手だからゴール手前でパスを受け取って最後を決める」等、みんなが自分の特徴を活かしてチームプレーで勝てるように考えることができました。結果、女子がドはまりして中休みの間もずっとタグラグビーをやっていたのが嬉しかったです。

↑タグラグビーを実践している授業中の様子(個人情報保護のため、一部モザイクを入れております)。
Pestalozzi Technologyは授業力向上のサポーター
コートが狭いと足の速い子しか活躍できないので、環境面はこちらで工夫し、あとは子供たち自身で「トライを決める」という目標達成のために誰が何をすべきか考えました。体力テストを通して自分の能力・特徴を知ることが出発点だと思います。足の速さも最重要な能力ですが、そんなに足が速いというわけではない子どもに私のディフェンスを抜かれたりしたので(笑)、俊敏性・瞬発力など「反復横跳び」の項目でチーム編成を考えてみてもいいかもしれません。
タグラグビー以外にも、「はんぎょボール」というアイディアをPT社員から提案してもらいやってみましたが、こちらも足の速い子に制限を設けるために「トライした数だけぬいぐるみを持たなければいけない」というルールを作り、運動が得意でない子以外も活躍できるような授業を実践できました。
PTは単なる「体力テストの業者」ではなく、私にとっては「授業力向上のサポートもしてくれる良き相談相手」といった存在です。これからもよりよい授業を目指し、PTにサポートしていただきながら、新しい取り組みにチャレンジしていきたいです。

↑横浜市立新羽小学校の校舎。小高い山の上に位置する。
(編集:Pestalozzi Technology株式会社)
導入事例一覧へ